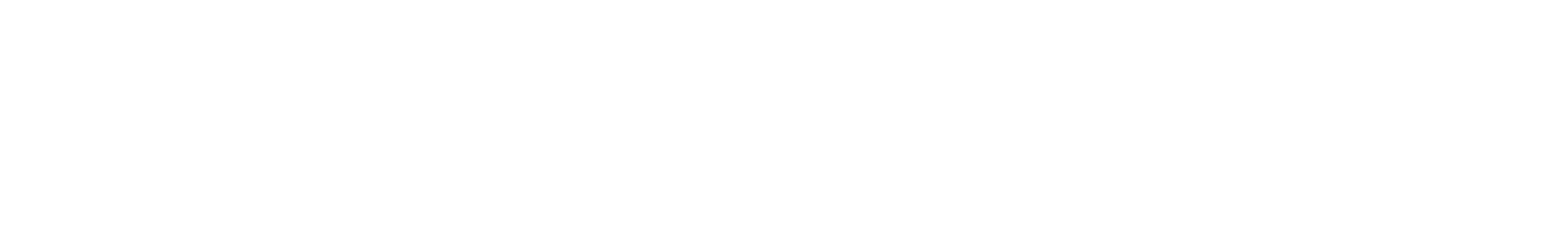コラム
【コラム】愛犬の耳トラブルを防ぐ|耳掃除の頻度と正しいケア方法
最近、愛犬が「耳を掻く仕草が増えた気がする」「耳からにおいがする」と感じたことはありませんか?
犬の耳は人間とは異なり、外耳道がL字型をしていて奥まった構造をしています。そのため、耳垢や汚れがたまりやすく、放置すると耳の中が蒸れて、細菌や真菌(カビ)の繁殖を招きやすくなります。特に耳が垂れている犬種は通気性が悪く、耳のトラブルが起こりやすい傾向があります。
さらに、犬種によって耳の形や耳垢の分泌量には個体差があります。正しい耳掃除の方法を知らずにいると、耳のかゆみや悪臭、さらには慢性的な耳炎へとつながることもあるため、それぞれの犬に合ったケアが重要です。
今回は、犬の耳掃除の重要性や犬種ごとの適切な頻度、そして獣医師が推奨する安全な耳掃除の方法について詳しく解説します。

犬の耳掃除が必要な理由
犬の耳は、形状や構造により非常に汚れがたまりやすい部位です。特に垂れ耳の犬は耳の中が密閉されやすく、通気性が悪いため、湿気がこもりがちです。立ち耳の犬であっても、耳垢の分泌が活発な場合や体質によって、耳の中の清潔を保つことは簡単ではありません。
耳掃除を怠ることで、まず耳垢が徐々に蓄積していきます。すると、耳の通気性がさらに悪化し、湿った環境が生まれ、細菌や真菌(マラセチアなど)が繁殖しやすくなります。こうした状態が続くと、耳が赤くなったり、かゆみや悪臭が現れるようになったりします。放っておくと、炎症が広がって外耳炎や中耳炎へと進行することがあり、症状が慢性化してしまうこともあります。
また、犬が耳をしきりに掻いたり、頭を振るような動作を頻繁に見せたりするようであれば、すでに不快感や痛みを感じているサインかもしれません。
耳掃除はただの「お手入れ」ではなく、愛犬の耳の健康を守るために欠かせない日常ケアのひとつです。ただし、頻繁すぎる耳掃除は耳の中の皮膚を傷つけてしまうこともあるため、正しい頻度と方法で行うことが大切です。
耳掃除の頻度|犬種や生活環境による違い
耳掃除の頻度は、犬種や耳の形、生活環境によって理想的なケアの頻度は異なります。
<垂れ耳の犬種>
ラブラドール・レトリバーやアメリカン・コッカースパニエルなどの垂れ耳の犬は、耳の中が湿りやすく通気性も悪いため、週に1〜2回の耳掃除が推奨されます。特に耳の中に毛が生えている犬種は、より汚れがたまりやすいため注意が必要です。
<立ち耳の犬種>
柴犬やジャーマン・シェパード・ドッグなどの立ち耳の犬は、耳の中に空気が通りやすく湿気もこもりにくいため、2週間に1回程度の耳掃除で十分です。
<アレルギー体質の犬や水遊びが好きな犬>
アレルギー体質の犬や、水遊びやシャンプーの機会が多い犬も注意が必要です。耳の中が湿りやすく、細菌が繁殖しやすい環境が整いやすいため、通常よりも耳のチェックと掃除の頻度を増やすことをおすすめします。
飼い主様は普段から愛犬の耳の状態をよく観察し、耳垢の量やにおい、かゆがる様子などが見られたら、必要に応じてケアの頻度を調整することが大切です。
正しい耳掃除の手順|獣医師推奨の方法
耳掃除を安全に行うためには、適切な道具を準備し、安全な方法で行うことが大切です。
<準備するもの>
まず用意しておくものは、犬専用の耳掃除液とコットンや柔らかいガーゼです。人間用の綿棒は、耳の奥を傷つける可能性があるため使用しないようにしましょう。
<耳掃除の手順>
①犬をリラックスさせる
まずは犬が安心できる環境を整えましょう。優しく声をかけながら、落ち着いた状態で始めることが大切です。
②耳掃除液を適量入れる
耳の入り口から数滴の耳掃除液を入れたら、耳の根元をやさしくマッサージします。L字型に曲がった外耳道の構造を意識し、耳の根元から顎の方向に向けて揉むようにしましょう。
③耳垢を浮かせる
耳掃除液をなじませることで、耳の中の汚れが浮き上がりやすくなります。この工程を丁寧に行うことで、無理なく汚れを取り除くことができます。
④汚れを拭き取る
浮かび上がった汚れを、コットンやガーゼで優しく拭き取ります。指に巻き付けたガーゼで、見える範囲だけをやさしく拭き取るのがポイントです。
⑤犬が頭を振るのを待つ
耳掃除後、犬は自然に頭を振ることで余分な液体を外に出そうとします。振ったあとは、残った液をもう一度ガーゼなどで軽く拭き取りましょう。
もし、犬が耳掃除を嫌がる場合は無理に行わず、耳を触ることに慣れさせるところから少しずつ始めてください。おやつを使って「耳掃除=良いこと」と印象づけるのも効果的です。
耳掃除で異常を見つけたら|動物病院を受診すべきサイン
耳掃除をしていると、日常的に犬の耳の状態をチェックすることができます。もし以下のような異常が見られた場合は、すぐに動物病院を受診しましょう。
・耳の中が赤く腫れている
・普段よりも強い悪臭がする
・耳垢がいつもよりベタついている
・耳垢が変色している
・耳を頻繁に掻く
・頭を何度も振る
・耳を触られるのを極端に嫌がる
これらの症状は、外耳炎や中耳炎の初期症状の可能性があります。耳炎を放置すると、症状が悪化し、治療が長引くことがあります。早期に異常を発見し、適切な治療を受けることで、耳の健康を長く保つことができます。
まとめ〜愛犬の耳の健康を保つためのケア習慣
犬の耳は、人間にはないL字型の構造をしているため、日常生活の中でどうしても汚れがたまりやすい場所です。そのため、定期的な耳掃除を行うことで、耳のトラブルを防ぎ、愛犬の健康を守ることができます。
ただし、すべての犬に同じ頻度や方法が当てはまるわけではありません。犬種や体質、生活環境に応じた耳掃除の頻度と方法を見つけることが、無理のない健康維持につながります。また、耳の異常に早く気づくためにも、普段から耳の様子を観察する習慣を持つことが大切です。
当院では、耳の健康診断や耳掃除の指導などについても詳しくアドバイスを行っております。「うまくできるか不安」「耳のにおいが気になる」といったお悩みがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。
川崎市中原区の「馬場動物病院」
TEL:044-777-1271
当院についてはこちらから